 株式会社フリービズ 代表取締役 角井秀行氏
株式会社フリービズ 代表取締役 角井秀行氏この記事はプロモーションが含まれていることがあります。
「これらの課題を解決するには、“インナーコミュニケーション”が重要」と、株式会社フリービズ 代表取締役の角井秀行氏は語る。長年にわたって企業の採用広報プランニングなどを支援してきた観点も踏まえた、「変化が激しい時代を勝ち残る」ためのインナーコミュニケーションとは?
目次
インナーコミュニケーションの活性化が、人材採用成功の鍵に
- ――前回、ビジョンの浸透におけるインナーコミュニケーションの重要性を教えていただきましたが、角井さんは「ビジョン=採用」というお考えを持っているそうですね。その理由を教えてください。
- 私が長い間、人材採用に関わるなかで、1つの“違和感”がありました。
企業の採用広報で多いのが、「当社は、こんなすごい実績を残しました」「大ヒット商品を開発しました」「こんな社員が活躍して、幸せになっています」など、ほとんどすべてが過去と現在の話です。
そこには、「こういうビジョンがあるから、これから入社する人たちと一緒に何がしたい」「5年後・10年後に、こんなことを一緒に成し遂げていたい」という“未来”の話がありません。当時から、入社する人たちにとって重要なのは「これから会社はどうなっていくのか?」という“未来”です。特にいまは変化が激しい時代ですから、極論すると、過去と現在のことは新しく入社する人には関係ないんですね。
本来であれば、一緒にビジョンに向かって進む“未来”を語らなければいけないのに、過去と現在から未来を語ろうとしない採用広報に違和感があったんです。
- ――過去や現在も大切ですが、未来こそが最も大切なんですね。
- そうです。人材の採用や育成で絶対にやってはいけないのが、「はしごを外す」ことです。新卒などの若い人たちは、「過去と現在に起きた(起きている)ことが繰り返される」と思って入社します。そういう方々が「想像していたのと違う」と感じると、ミスマッチが起きて退職につながってしまいます。
だからこそ、インナーコミュニケーションを通じてビジョンを社内に浸透させて、採用の際にもビジョンとその実現に向けた取り組みをしっかり伝えていくことが重要です。そのように“未来”を語り、一緒に前に進むという点で、ビジョンと採用は切っても切り離せないものだと思っています。
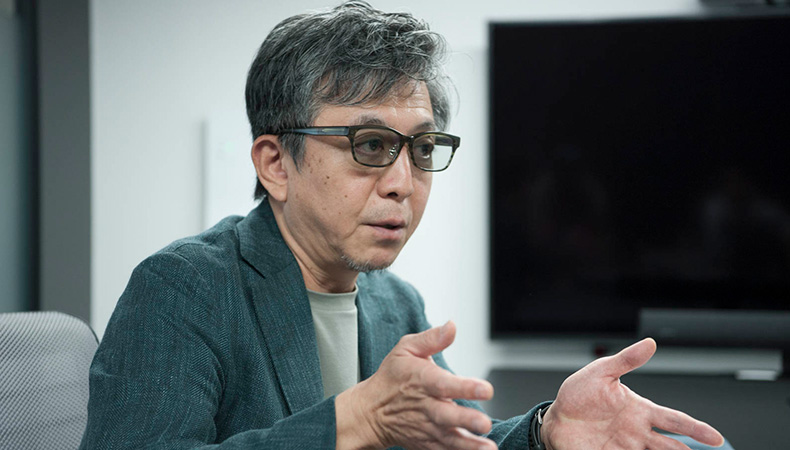
採用以上に、入社後のコミュニケーションを重視すべき
- ――角井さんが採用など人材関連の企業支援に長く携わってきた観点から、HR(Human Resources)の施策でインナーコミュニケーションを活かすためのヒントを教えてください。
- まずは採用時に、インナーコミュニケーションで社内共有されているビジョンなどをきちんと伝えて、「自分たちは○○を目指すから、こんなふうにあなたと一緒にやっていきたい」ということを語って、それに本当に共感してくれる人材を採用することが理想です。
しかし、当然ながら、採用だけで人材に関する課題を100%解決できるわけではありません。長期的な視点でとても大切なのは、“入社後のコミュニケーション”です。
新卒入社でも中途入社でも、人は入社後に変わっていきます。ですから、採用よりも「入社後、会社と社員が一緒に、どう変わっていくか」ということが大切です。そのためにも、経営者の方やマネジャー・リーダー層の方が一枚岩になってインナーコミュニケーションを取れる体制が必要です。
企業が注力すべきことは、学生1人1人をきちんと見極めて採用することだけではありません。「こういう志や期待を持って入社してくる人たちと一緒に、どう成長していくか」を社員と共に考えることが大切だと私は思います。
- ――新入社員の退職の意思を企業側に伝える“退職代行サービス”が話題になりましたが、そのような企業姿勢やインナーコミュニケーションがあればそういった問題も防げるのですね。
- その通りです。インナーコミュニケーションによって心理的安全性が確立されていれば、他者を通して退職の意思を伝えることはもちろん、それ以前にいろいろな相談ができます。
また、若手社員にとって「自分のキャリアについて、思うように発信できている」という状況があって、マネジメント層としては「部下のキャリアマネジメントを適切にできている」という状況であれば、退職しようと思っても、むしろ積極的に相談をしにくると思います。
情報過多の時代に、企業が知るべき学生の現状
- ――学生さんと1on1でキャリアカウンセリングを行うなかで感じることや、新入社員など若い方とインナーコミュニケーションを取るために企業が知っておくべきことを教えてください。
- 学生をはじめ、若い方とお話ししていて感じるのは、「以前に比べて“情報量”が圧倒的に多い」ということです。みなさん、情報に対するセンサーがすごく敏感で、SNSなどインターネットを通じていろいろな情報を知っています。
でも、「その情報を、どんな軸で処理していくか」という点は未熟だと感じます。学生さんと接していてよくあるのは、「ネガティブ情報を、真に受けてしまう」というパターンです。
ネガティブ情報は広がりやすいので、その情報を知って、たとえば「この会社はインターンシップの選考に落ちたら就職面接でも落とされるという噂は本当ですか?」と聞かれることがよくあります。
その噂の真相がわからない私としては、まず「もし本当だとしたら、インターンシップを諦める?」と尋ねるようにしています。そして、「失敗してもいいから挑戦してみて、駄目なら諦めがつくし、そのために準備をしたことは自分の経験になる」と話しても、どうしても二の足を踏んでしまうんですね。
- ――ネガティブな情報に影響されて、最初から諦めてしまうのですね。
- そうなってしまうこと自体は、仕方がないと思います。なぜなら、得られる情報量が本当に多いからです。このような若い方の傾向は、採用にあたって理解しておくだけでなく、入社後も心に留めておく必要があります。
以前は、「何も知らない状態から、常に先輩の横で仕事を見て、質問しながら学ぶ」のが普通でした。それが当たり前と考えるベテランの方は、いまでも多くいらっしゃいます。ですが、いまは仕事に関する情報をネット上で簡単に得られます。
ですから、「時代や社会環境が変化して、思考パターンや行動パターンも変わってきている」と理解することが必要です。
また今後は、若い方を「Z世代」といったくくり方で捉えることはできなくなってくると思います。1人1人の個性や多様な価値観を認めなければインナーコミュニケーションは確立できないので、「○○世代」とひとくくりにして若い方と接することは危険です。

若手との会話で重要な“will”と“フェアウェイゾーン”
- ――いまは、パワーハラスメントなどの問題もあって、若手とベテランとの関係性が難しい時代になっています。異なる世代間でのインナーコミュニケーションを成功させるポイントを教えてください。
- 若手とベテランの違いは、「経験・キャリア・専門性があるか・ないか」だけだと思います。ですから、若手の方と話すときは「何がしたい」「どうしたらいい」という“will”で会話することが重要です。
上司の仕事は、若手社員の“will”に対して、「そうか、わかった。でも、ここまではできても、ここからはできないよ」という“フェアウェイゾーン”を示すことです。そして、「このフェアウェイゾーンのなかで、このルールを守れば、やりたいことをやっていい」ときちんと伝えて、納得してもらう必要があります。
若手に対して一番やってはいけないコミュニケーションが、「そういうことがしたいのなら、やってみていいよ」と伝えて、その後に協力やサポートをしないことです。また、そもそも実現できないことなのに「やっていい」と言って、若手の方に「はしごを外された」と感じさせるのも避けなければいけないと感じています。
- ――現在の社会の風潮もあるのかもしれませんが、若手に対して「それ、いいね!」と言う上司の方もよくいらっしゃいますよね。
- 安易に答えた結果として、期待が裏切られた形になると信頼を失います。ですから、若い方とのコミュニケーションを行ううえで、特にその部分を気遣うことが大切です。
また、いろいろな企業様の行動指針をつくっていて「挑戦しよう」「0から1をつくろう」といったキーワードがよく出てきますが、実際に挑戦できることは限られていると思います。ですから、会社としても、若手に対して“挑戦できる範囲”を明確に示すことが重要です。
働き方改革を通じて、何を“語れる”か

- ――企業にとって働き方改革は必須ですが、働き方改革とインナーコミュニケーションにはどのような関連性がありますか。
- 最近、人材採用のために自社の働き方改革をアピールする際に「ハイブリッドワーカーやポートフォリオワーカーなどの副業・複業OK」「将来的な転職も歓迎」と打ち出す企業が増えています。その働き方改革自体は良いことですが、「なぜ、その取り組みをしているのか」を語れることが非常に重要です。
たとえば、「多様な知識を身につけてほしいから、こんな経験をこういう部分に活かしてほしいから、副業・複業OK」という部分まで社員の方に説明できることが重要だと思います。そのような状態こそが、働き方改革におけるインナーコミュニケーションの問題です。
- ――これまでに角井さんが関わった、働き方改革とインナーコミュニケーションに関する事例があれば教えてください。
- 昨年、ある法人様から「“半官半民”の組織なので、働き方改革をしなければいけない。施策を考えたいので、社員ミーティングを実施して具体的な施策を決めてほしい」というご依頼をいただきました。
社員で働き方改革のための制度などを考えるのは、とても良い取り組みです。ですが、そもそも「しなければいけない」ありきでは、働き方改革は成功しません。そのことを最初にお伝えして、「どういう想いを持って、働き方改革を進めるか」を一緒に考えるところからスタートしました。
「なぜ、この施策を行うのか」「働き方改革を行うことによって、社員にどんなメッセージを伝えたいのか」「働き方を変えることで、従業員にどう変わって欲しいのか」という理由や背景、想いなどを語れなければ、“本当の働き方改革”はできないと思います。
そして、この“語れる”ということが、インナーコミュニケーションで一番重要です。
- ――「世の中の風潮に合わせて、自分たちもやらなくちゃいけない」という義務のような感じで始める企業もありそうですね。
- そうなんです。私が経営陣や人事、経営企画の方々とお話しするなかで、「業務がすごく増えてきていて、大変だな」と感じます。「やらなきゃいけないから、外注しよう」という気持ちもよくわかりますが、働き方改革を成功させるためには“自分たちが語れるもの”をつくることが大切だと思います。
また、働き方改革におけるインナーコミュニケーションで重要なポイントがもう1つあります。
前回、ビジョン浸透に関するインナーコミュニケーションの課題として、「突然、経営陣から新しいビジョンを告げられて、従業員が共感できない」という事例をご紹介しました。しかしビジョン以上に、働き方改革こそ、会社の上層部が決めて社員に通達するのは効果的ではないと私は考えています。
当事者である社員が意見や要望を言う前に、自分たちが知らない間に決められたことが突然出てきても歓迎できないと思いませんか?
- ――それが良い制度であっても、事前に相談や説明をしてもらったほうが納得感は高いですね。
- たとえば、一緒に食事に行こうというときに、「何が好きですか」「何を食べたいですか」と聞かずに「焼肉屋を予約しておきました」というのと同じで、釈然としませんよね(笑)。
ですから、会社側が「こんな考えや事情を持つ人が、こういう理由で休暇を取って、こんなことをしている」というシーンをイメージできているうえで、そのシーンを社員に語りながら、「こういうことをやろうと思っているんだけど、どうですか?」とコミュニケーションできることが重要です。
- ――社員とのインナーコミュニケーションを通じて意見を取り入れて、制度などをつくることが必要なのですね。
- そうですね。いまの働き方改革の1番の問題は、そのようなコミュニケーションができていないことだと思います。「自分が何をしてほしいか」を聞かれない限り、社員は納得できませんから。

自社の“転換”に即対応できる社員が多い企業が勝ち残る
- ――自社の業績や生産性の向上、人手不足への対応などで、インナーコミュニケーションの優先順位を低くせざるを得ない企業もあると思います。今後、インナーコミュニケーションを重視する会社としない会社では、どのような差が生まれるとお考えですか?
- いまのように変化が激しい時代・社会に対応するためには、自社のビジョンや方針、戦略などを転換するスピードが速まって、転換の頻度も増えていくと思います。
そういった「新しいことを始めよう」「新規事業に着手しよう」というときに、すぐに「よし、行くぞ!」というモードに入れる社員が多い会社は勝ち残っていくはずです。
- ――前回、「組織の人材比率は、“積極的に動く2割”“平均的な6割”“意欲が低い2割”にわかれる」という『262の法則』のお話がありました。その最初の2割から、さらにどう増やしていくかということがキーポイントになるということですね。
- そうです。「転換を行うときに、すぐに行動してくれる2割を生めるかどうか」が鍵になります。日頃から「こういう状況になったら、こうしよう」ということを話し合えていれば、それを理解して最初の2割が率先して動き、周囲も反応してくれます。
そのためにも、自社の状況をきちんと話し合えるインナーコミュニケーションを確立して、事業が成長していく基盤だと認識していただきたいと思います。
文・あつしな・るせ
写真・大井成義

- 角井 秀行(かくい ひでゆき)株式会社フリービズ
- 大阪大学経済学部を卒業後、株式会社リクルートに入社し、約23年間、大手企業を中心とした新卒・中途採用広報のプランニング、採用ブランディング支援などに従事。広告制作部門の部長を務めたのちに独立し、学生など若年層向けキャリア支援事業や企業研修講師・ファシリテーションなどを手がける。2017年、「『自分を自由に表現する』個人に溢れた社会・組織をつくる」という事業コンセプトを掲げ、株式会社フリービズを設立。企業の理念・ビジョン策定、その浸透のための研修やワークショップ、企業研修講師・ファシリテーション、斡旋キャリアカウンセラーなどに携わる。GCDF-Japanキャリアカウンセラー。国家資格キャリアコンサルタント。



