参加者全員が動く会議【第7回】
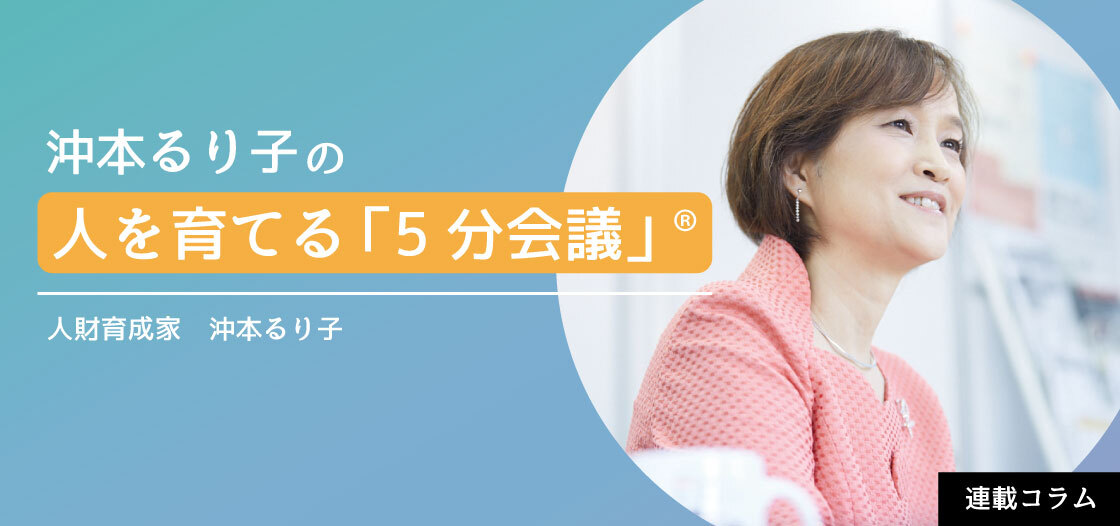
人財育成家 沖本るり子
この記事はプロモーションが含まれていることがあります。
こんにちは。「5分会議」🄬を活用した人財育成家の沖本るり子です。
会議を運営する場合、一人に依存させないことです。参加者全員で運営しましょう。そこで、どうすればいいのかをお話ししましょう。
- ミニ会議に必要な「三役」
- 参加者の方向性が揃ったところで、いよいよミニ会議を進めていきます。この段階で、ミニ会議に欠かせない「三役」を決めましょう。必要な係とそれぞれの役割は次のとおりです。
- ◇進行係
ミニ会議の議事進行を担う。
会議の目標達成のため、参加者の意欲や時間意識、集中力を高める工夫をしながら進める。
- ◇時計係
ミニ会議中の時間管理を行う。
制限時間に合わせてアイデア1件当たりの発言時間を算出し、発言や議論が時間内に収まるようにキッチンタイマーをセットしたり、秒単位で参加者の発言時間を管理したりする。
- ◇メモ係
ミニ会議中の参加者の発言を、ホワイトボードシートに書いていく。
- 参加者の多い会議で、複数のテーブルでミニ会議を行う場合は、それぞれのテーブルごとに三役を決めます。
- このほか、部屋の温度調整をする「空調係」やホワイトボードシートのメモをカメラで記録する「議事録係」、ペンや付箋など必要なものを準備する「備品係」など、全員が何かしらの係になるように分担します。
- そしてミニ会議には、係になった人たちも参加します。進行係は全体の流れを調整しながら、発言の順番がきたら自分の意見を言います。
- もっとも大変なのは、メモ係でしょう。みんなの意見を聞きながら次々と箇条書きにまとめ、書いているそばから自分の意見をまとめなければなりません。頭も耳も目も手もフル回転です。
- キッチンタイマーを2個用意する理由
- 「5分会議」🄬では、時間管理が何より肝になります。各会議の時間も、プログラムに充てられた時間を単純に割るだけではうまくいきません。
- たとえば、アイデアが6件出ていて、「いいところ出し会議」に5分間割り当てられたとしましょう。
- 「1アイデアに与えられた発言時間は50秒」となると、ほとんどの場合は5分では足りなくなります。というのも、「はじめ!」と同時にアイデア出しはできないからです。したがって、前後の予備時間も考慮すると、1アイデアに要する時間は45秒程度といったところでしょうか?仮に45秒で6アイデアだと、270秒。
- ところでテーブルの配置のところで、キッチンタイマーはテーブルごとに2個用意すると説明しました。これには理由があります。
- 1つはミニ会議の時間を計るため、もう1つは1アイデアに対しての制限時間を計るためです。先ほどの例では、「各アイデアのいいところ出し会議」に与えられた5分を1つめのキッチンタイマーにセットし、もう1つのキッチンタイマーには45秒をセットします。
- 「5分会議」🄬を繰り返すと、日ごろから時間を意識して過ごせるようになります。第1回で紹介した吉村では、会議室の外でもキッチンタイマーが大活躍。目標時間をセットして日々の業務に臨んでいるそうです。時間内に終わらせようと集中するので、効率化にもつながります。
- 輪番制でみんなが三役
- 先ほど、「5分会議」🄬では全員が何かしらの役割を持つことをお伝えしました。その究極が、「三役の輪番制」。ミニ会議ごとに三役を交代するのです。
- たとえば「いいところ出し会議」が終わり、「問題点出し会議」に移るタイミングで、チーム内で時計回りに役割が移るといったイメージです。さっきまで進行係だった人が時計係に、時計係だった人がメモ係に……といった具合で、まったく違う役割を担います。
- このやり方なら、参加者全員が均等に三役を担うことになります。
- 社歴や年齢は関係ありません。新人でも進行を担当しますし、社長でも必死にホワイトボードシートにメモをし続けます。ベテラン社員になると、周りの意見をよく聞いて要約するという場面も少なくなるものです。会議が読み書きのスキルを鍛える、貴重な場となるでしょう。
- これを1回の会議で何度も繰り返すのですから、頭のモードが頻繁に切り替わります。脳の活性化にもつながり、建設的なアイデアもひらめきやすくなります。
- 熱が入ると、自然と立つようになる
- 「5分会議」🄬の研修を行うと、中盤以降で特徴的な光景を目にします。最初は椅子に座っていた参加者たちが次第に席を立ち、前のめりに立ったまま議論を展開していくのです。輪番制でいろいろな係を担当すると、能動的に関わることの重要性に気づきます。進行係になると場を温めることの難しさを痛感し、時計係をやることで時間をオーバーして話すことが、どれだけ進行の妨げになるかがわかります。
- そしてとりとめなく話をされたときの、メモがいかに大変なことか! 会議を運営する立場を経験することで、協力的になっていきます。
- 参加者に主体性が芽生えると、会議はどんどん楽しくなります。積極的に意見を出そうとするし、人の話も最後まで聞くように。さらには何かしらの役割を担っていますから、だんだんとヒートアップしてくるのです(すると、たいていの場合、最初に用意した名札が机の脇に寄せられていきますが、それでも構いません)。
- これまで行われた「5分会議」🄬の様子を見ていると、ミニ会議が次の議題に移り三役を交代するタイミングで、参加者たちが席を移動するようになります。ものを次の人に渡すよりも、自分たちが動いたほうが早いからです。無駄な時間をできるだけ削いで、議論に集中したいと自然と体が動くようになるのです。
- オンライン会議でも、小チームに分かれ、各チーム内で役割分担をし会議を行います。この場合、1つの会議でチーム分けができない場合、チーム分の会議を立ち上げておけばよいのです。考え方は対面会議と同じで、オンライン会議のツールの機能をうまく活用して応用しましょう。
※本記事は『期待以上に部下が育つ高速会議』から抜粋・再編集したものです。
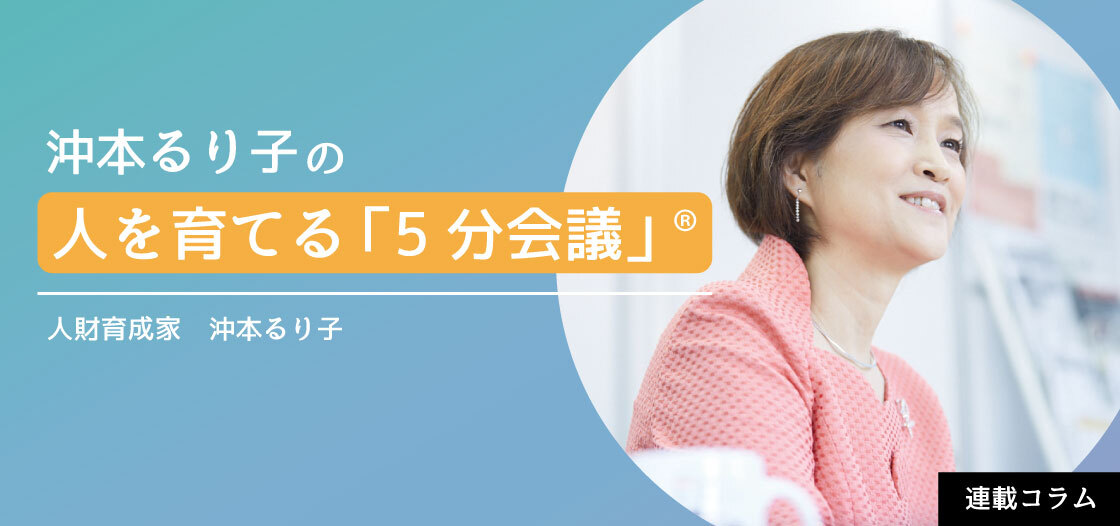 人財育成家 沖本るり子
人財育成家 沖本るり子